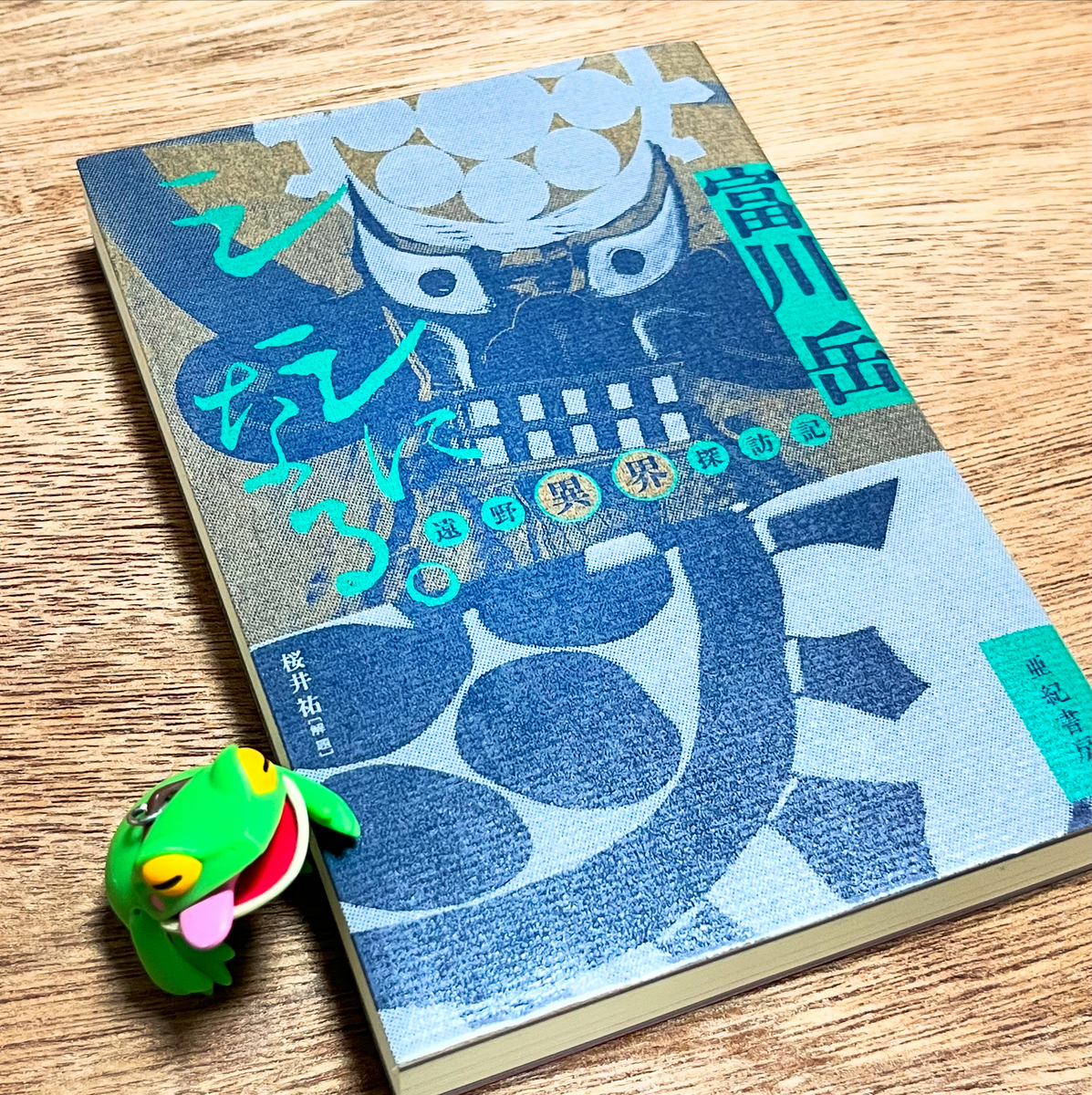「はだかんぼうたち」
江國香織
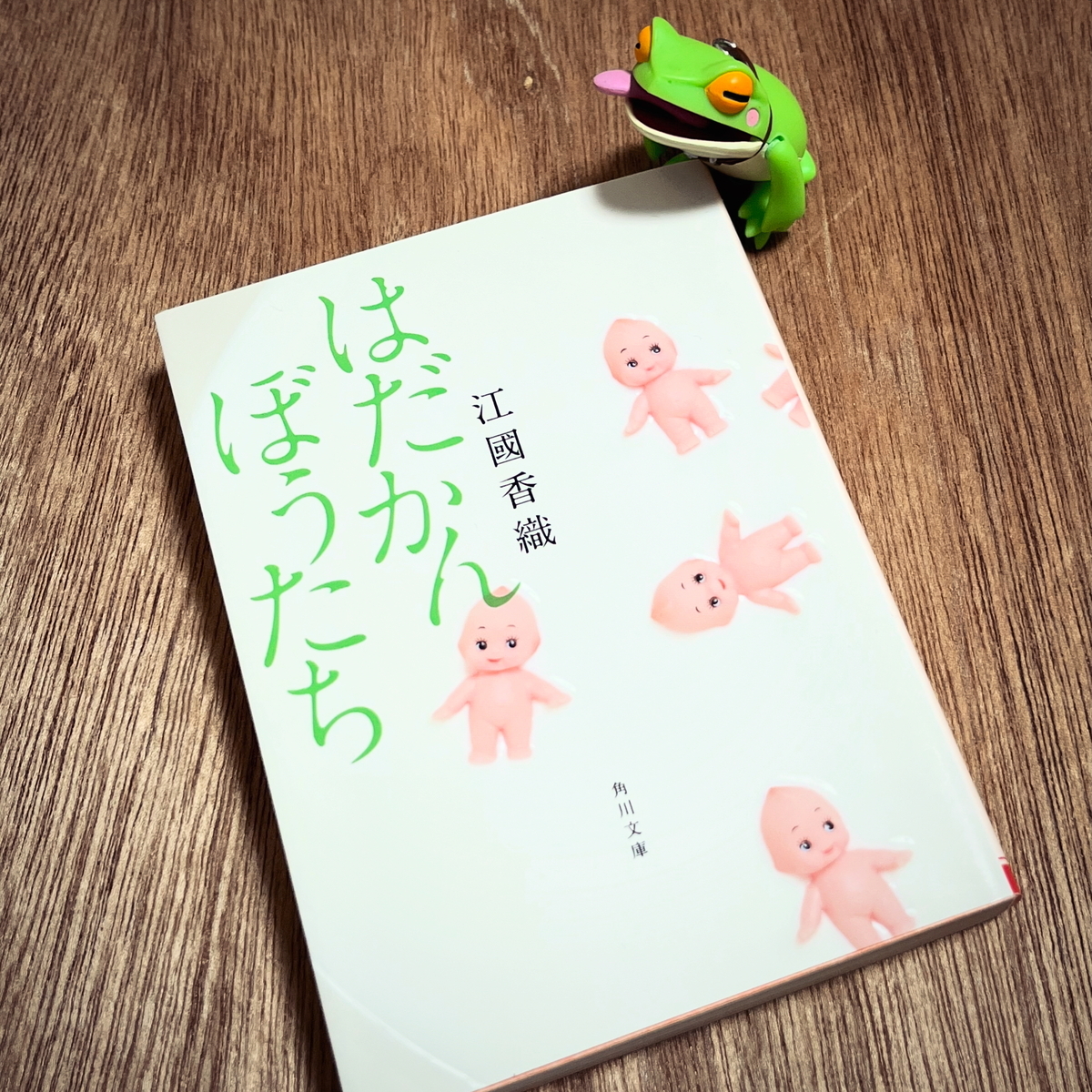
ざまあみろ。
言い方は悪いが、江國さんの書く母親像に自分の母親を重ね合わせてそんなことを思ったりする。いや、母親ではないか、親戚中の自分より年上のすべての女性か。
決して悪い人ではないのだけど、娘の結婚(という名のしあわせ)を待ち望み、自分の理解できないことは聞かなかったことにする。悪気はなく傷つくことを言い放つ。もしや江國さんも、と思わずにはいられないほど。
母親の思った通りには娘は育たないのだ。みんなそうじゃないだろうか。
好きなものに囲まれて、自分で稼いだお金で装身具を買い、想いの人と唇を重ね、自分の足で立って生きる。もう成人して親元を離れているし、自分の人生を自分で歩んでいるのだ。
それなのに。
それなのに、結婚していないことや子どもがいないことに罪悪感を感じるのはなぜだろう。世間体というプレッシャー、周りからの目には見えない謎の期待。自分で選んだ道なのに。私、何も悪いことはしていないのに。
だからこそ、江國さんの小説に救われる。読んでいる時だけ、呪縛が解ける。
きっと、桃には「自分の好きにしていいのよ?」、鯖崎には「そんなことよりも、うまいメシでも食べに行こうよ」、と言われるだろう。そして「人それぞれ、想いは違って当然。そうでしょ?それにね、自分の肉体は、他の誰のものでもなく自分のためだけにあるものだから」と、内緒話をする少女のように江國さんが囁く声が聞こえる気がする。私はそれを聞いてほっとするのだ。